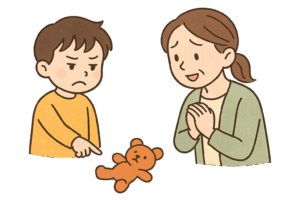「境界知能」とは?知的障害との違いや支援のポイントについて
はじめに
「境界知能」という言葉を聞いたことがありますか? 知的障害と健常のあいだに位置する知的能力のことを指します。 学校や社会生活の中で、理解のペースがゆっくりだったり、複雑な情報を整理するのが苦手だったりする場合があります。
本記事では、境界知能の特徴や知的障害との違い、そして支援のポイントをわかりやすく解説します。
境界知能とは
境界知能とは、知能指数(IQ)が約70〜85の範囲にある状態を指します。 知的障害とまではいえないものの、平均よりやや低い認知能力を持つため、学習や社会的適応の面で困難を感じやすい傾向があります。
ただし、「知能が低い」ということではなく、情報処理のスピードや抽象的思考に苦手さがある一方で、得意な分野を持つことも多くあります。
知的障害との違い
知的障害はIQ70未満を目安とし、日常生活や学習に広範な支援を必要とする状態を指します。 一方、境界知能はIQ70〜85程度であり、支援が必要な場面と自立できる場面が混在します。
そのため、周囲からは「少し努力が足りないだけ」と誤解されやすく、適切な理解とサポートがないと自己肯定感の低下につながることもあります。
境界知能の特徴
- 複数の情報をまとめるのが苦手で、整理に時間がかかる
- 文章の要点をつかむのに時間がかかる
- 一度に多くの指示を出されると混乱しやすい
- 計画的に行動することが難しい
- 周囲の状況を読むのが苦手で誤解されやすい
境界知能の子どもたちは、理解に時間がかかる一方で、繰り返しの学習や丁寧な説明で着実に力をつけていくことができます。
支援や接し方のポイント
家庭や学校での工夫
- 一度に伝える情報を少なくする
- 「やること」を目で見てわかる形にする(メモやチェックリスト)
- 小さな成功体験を積み重ねて自信を育てる
- 失敗を責めず、ペースに合わせて関わる
支援のポイント
- 「わかるまで待つ」姿勢を大切にする
- 周囲が代弁するのではなく、本人が自分の言葉で表現できる環境を整える
- 本人の得意分野を伸ばし、苦手を補う支援計画を立てる
クラップでの取り組み
クラップでは、境界知能のお子さまも含め、一人ひとりの理解のペースや得意分野に合わせた学習支援を行っています。 学校の学習内容を丁寧にサポートし、わからない部分をそのままにしないよう、個別学習とグループ活動を組み合わせています。
また、SST(ソーシャルスキルトレーニング)を通じて、コミュニケーション力や自分の考えを伝える力を育てることも重視しています。
保護者との面談や日々のやりとりの中で、家庭での接し方のアドバイスや進捗共有も行いながら、安心して通える環境づくりを心がけています。
まとめ
境界知能は「できない」ではなく、「理解に時間がかかる」特性を持つだけです。 周囲の理解と支援があれば、子どもたちは確実に力を伸ばしていけます。 クラップでは、お子さまのペースを尊重しながら、自信を育む支援を続けています。
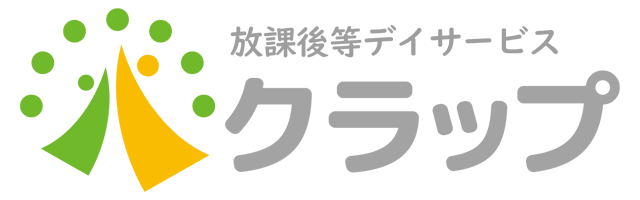
-300x200.png)